2018年11月29日
八丸で鶏白湯醤油ラーメンを食べてみました。
平成30年度第2回静岡鍼灸師会中部支部の講習会前に麺や八丸に昼食を食べに立ち寄りました。
このお店は食べログで見つけたお店で、入店したときに何が美味しのか分からないので、お店のお勧めのメニューを注文しました。
この日注文したのは、鶏白湯醤油ラーメンです。
商品が出てきた時にまずスープから食してみました。

スープはコクがありますが、アッサリ醤油味がして美味しい。
また、分厚いチャーシューが3枚ついており、これも美味しかったです。
麺は細麺で、少し硬さがあるようでした。
全体的には、美味しいラーメンでした。
また、行く機会があれば来店したいと思います。

このお店は食べログで見つけたお店で、入店したときに何が美味しのか分からないので、お店のお勧めのメニューを注文しました。
この日注文したのは、鶏白湯醤油ラーメンです。
商品が出てきた時にまずスープから食してみました。

スープはコクがありますが、アッサリ醤油味がして美味しい。

また、分厚いチャーシューが3枚ついており、これも美味しかったです。

麺は細麺で、少し硬さがあるようでした。
全体的には、美味しいラーメンでした。
また、行く機会があれば来店したいと思います。


2018年11月24日
今後の健康産業や医療を含むサービス業のマーケティング戦略
平成30年11月18日(日)に平成30年度第2回 公益社団法人静岡県鍼灸師会中部支部学術講習会が静岡医療学園専門学校の教室で開催されました。
今回は、『今後の健康産業や医療を含むサービス業のマーケティング戦略』と題して、静岡県立大学経営情報学部教授の岩崎邦彦先生の講演が行われました。
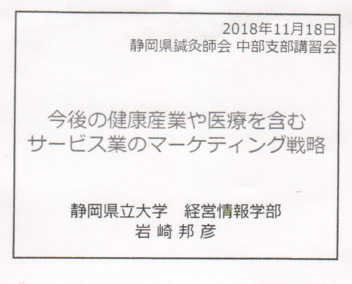
今回はその概要をお話します。
まず、マーケティングとは、顧客を維持生み出すことである。
マーケティングのポイントは、価値である。
例をして化粧品を買う理由は、「きれいになる。」「変身できる」とお客さんは商品を買うのではなく、“綺麗になること”を買う。
以前のお茶業界では、急須でいれるお茶が減っていることに危機感を持ち『俺は葉っぱで飲む」という広告をしていた。
これは、『売りたい』と気持ちが出ている。
販売の発想とは、今ある商品を売り込もう
マーケティングでは、どうしたら顧客が買いたくなるのか?
はじめに“顧客”ありきである。
何を売るのではなく、“なぜ買うのか”着目する。⇒お客さんの価値
小さな事業所のマーケティングのNGは無難、平凡、普通、まあまあ、そこそこ
収入があがらず何でもある世の中のでは、無難=難
小が大を超えるには、尖がりが不可欠
病院に関するイメージは、痛み、不安=怖い
医療における事業の再定義は、不安解消業

病院にあったらよいと思うサービスは?
不安を取り除くカウンセリングサービス、ゆったりくつろげるラウンジやカフェ等。
以上が概要です。
今回21世紀の医療のマーケティング戦略を聴講でき勉強になりました。
そして、今回講演に応じてくださいました岩崎邦彦先生に感謝を申し上げます。
ありがとうございました。
今回は、『今後の健康産業や医療を含むサービス業のマーケティング戦略』と題して、静岡県立大学経営情報学部教授の岩崎邦彦先生の講演が行われました。
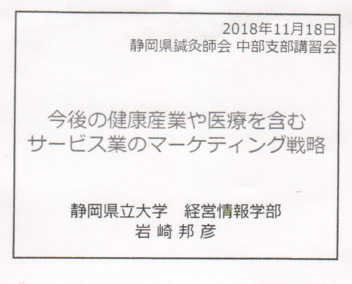
今回はその概要をお話します。
まず、マーケティングとは、顧客を維持生み出すことである。
マーケティングのポイントは、価値である。
例をして化粧品を買う理由は、「きれいになる。」「変身できる」とお客さんは商品を買うのではなく、“綺麗になること”を買う。
以前のお茶業界では、急須でいれるお茶が減っていることに危機感を持ち『俺は葉っぱで飲む」という広告をしていた。
これは、『売りたい』と気持ちが出ている。
販売の発想とは、今ある商品を売り込もう
マーケティングでは、どうしたら顧客が買いたくなるのか?
はじめに“顧客”ありきである。
何を売るのではなく、“なぜ買うのか”着目する。⇒お客さんの価値
小さな事業所のマーケティングのNGは無難、平凡、普通、まあまあ、そこそこ
収入があがらず何でもある世の中のでは、無難=難
小が大を超えるには、尖がりが不可欠
病院に関するイメージは、痛み、不安=怖い
医療における事業の再定義は、不安解消業

病院にあったらよいと思うサービスは?
不安を取り除くカウンセリングサービス、ゆったりくつろげるラウンジやカフェ等。
以上が概要です。
今回21世紀の医療のマーケティング戦略を聴講でき勉強になりました。
そして、今回講演に応じてくださいました岩崎邦彦先生に感謝を申し上げます。

ありがとうございました。

2018年11月20日
H30.11.21~H30.12.4までの営業のお知らせ
ケアマネージャーの仕事の都合により、営業時間を変更させていただきます。(H30.11.21-H30.12.4)
11月22日(木) 9:00~12:00 14:00~16:00
11月24日(土) 9:00~12:00 14:00~19:00
11月29日(月) 9:00~12:00 14:00~19:00
11月30日(金) 午前休診 14:00~19:00
11月4日(火) 9:00~12:00 14:00~19:00
上記の以外の期間内営業H30.11.21-H30.12.4)については、日曜日を除いて、18:30以降に電話があったときに対応させていただきます。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご協力をお願いします。

2018年11月16日
認知症について考えてみよう ~認知症のケアについて~
今回は、認知症のケアについて考えてみましょう?
もし、あなたの家族の方が認知症になった時に、どう対応しますか?
多くの方は、「どうしてこんなこともできないのか? 」と思い、ちぐはぐな行動をしている当事者に怒ってしまうかもしれません。
」と思い、ちぐはぐな行動をしている当事者に怒ってしまうかもしれません。
しかし、このような対応は、健常者の目線でみているから理解できないのです。
認知症の方の目線で見れば、ご本人は安心して、ちぐはぐな行動も少なくなっていきます。
例えば、あなたががんと診断されたときにどんな気持ちになりますか。
おそらく、「自分だけがどうして病気になったのか、自分はどうなってしまうのか? 」と自問自答するのではないでしょうか?
」と自問自答するのではないでしょうか?
そして、目の前の現実から目を背け、「もっと違う医師に診てもらえば、違う診断がでるかもしれない。」と思うかもしれません。
このように、未来の不安、病気を否定するような気持ちになるのではないでしょうか?
認知症の方も「何をしていようのかわからない、いったい自分をどうなってしまうのか」と不安感を訴える方がいます。
その中には、病気を否定し、正常に振る舞うことで、自分の気持ちを正常に保とうとする方もいます。
そして、がんも認知症の方もそうですが、その気持ちを受け止めて、サポートしてくれる存在がその人の気持ちを落ち着かせる最大の治療となります。
といっても、認知症の方がどうなっているのか、分かりにくいのも事実です。
それは、認知症の方しかわからないからです。
認知症の方で、自らの体験を講演している代表的な方にオーストラリア在住のクリスティーン・ブライライデンさんがいます。
彼女は、オーストラリア政府の高官として仕事をしたのですが、46歳の時に認知症と診断されます。
その当時、夫と離婚をして、仕事をしながら3人の娘さん(当時長女19歳、次女13歳、三女9歳)を育っていました。
そして、強いストレスを受け、偏頭痛を訴えていた時期でした。
その偏頭痛の診察を受けた時に、認知症と診断され、医師から仕事から身を引くように説得されます。
また、認知症と診断されてから認知症協会に問い合わせを行いますが、当時は認知症の家族をサポートすることは行わたもの、認知症本人のケアがないことに愕然とします。
将来への不安や人間としての尊厳を受け入れないことに悲観しながらも、この状況を変えていこうと講演活動や本を出版します。
第1冊は、自分にある恐怖の気持ちをタイトルに表現した『私は誰になっていくの?』を出版します。
その2年後に夫となるポールさんと結婚をして、2冊目の本『私は私になっていく』を出版します。
このようにブライデンさんは、自分を理解するパートナーとめぐり合い、精神が落ち着を取り戻すして認知症と向き合い、充実した生活を送ることが出来るようになったのです。
ですから、認知症の方にとって自分を理解してくれる存在が大切だとわかると思います。
しかし、いざ認知症の方をケアしようと思うとなかなか大変で忍耐がいりますね。
次回は、認知症ケアの方法について、お話をしたいと思います。
そして、クリスティーン・ブライライデンさんについては、ネットで検索すれば本やDVDの情報が得られますので、興味ある方は、検索をしてください。
もし、あなたの家族の方が認知症になった時に、どう対応しますか?
多くの方は、「どうしてこんなこともできないのか?
 」と思い、ちぐはぐな行動をしている当事者に怒ってしまうかもしれません。
」と思い、ちぐはぐな行動をしている当事者に怒ってしまうかもしれません。しかし、このような対応は、健常者の目線でみているから理解できないのです。
認知症の方の目線で見れば、ご本人は安心して、ちぐはぐな行動も少なくなっていきます。
例えば、あなたががんと診断されたときにどんな気持ちになりますか。
おそらく、「自分だけがどうして病気になったのか、自分はどうなってしまうのか?
 」と自問自答するのではないでしょうか?
」と自問自答するのではないでしょうか?そして、目の前の現実から目を背け、「もっと違う医師に診てもらえば、違う診断がでるかもしれない。」と思うかもしれません。
このように、未来の不安、病気を否定するような気持ちになるのではないでしょうか?
認知症の方も「何をしていようのかわからない、いったい自分をどうなってしまうのか」と不安感を訴える方がいます。
その中には、病気を否定し、正常に振る舞うことで、自分の気持ちを正常に保とうとする方もいます。
そして、がんも認知症の方もそうですが、その気持ちを受け止めて、サポートしてくれる存在がその人の気持ちを落ち着かせる最大の治療となります。
といっても、認知症の方がどうなっているのか、分かりにくいのも事実です。
それは、認知症の方しかわからないからです。
認知症の方で、自らの体験を講演している代表的な方にオーストラリア在住のクリスティーン・ブライライデンさんがいます。
彼女は、オーストラリア政府の高官として仕事をしたのですが、46歳の時に認知症と診断されます。
その当時、夫と離婚をして、仕事をしながら3人の娘さん(当時長女19歳、次女13歳、三女9歳)を育っていました。
そして、強いストレスを受け、偏頭痛を訴えていた時期でした。
その偏頭痛の診察を受けた時に、認知症と診断され、医師から仕事から身を引くように説得されます。
また、認知症と診断されてから認知症協会に問い合わせを行いますが、当時は認知症の家族をサポートすることは行わたもの、認知症本人のケアがないことに愕然とします。
将来への不安や人間としての尊厳を受け入れないことに悲観しながらも、この状況を変えていこうと講演活動や本を出版します。
第1冊は、自分にある恐怖の気持ちをタイトルに表現した『私は誰になっていくの?』を出版します。
その2年後に夫となるポールさんと結婚をして、2冊目の本『私は私になっていく』を出版します。
このようにブライデンさんは、自分を理解するパートナーとめぐり合い、精神が落ち着を取り戻すして認知症と向き合い、充実した生活を送ることが出来るようになったのです。
ですから、認知症の方にとって自分を理解してくれる存在が大切だとわかると思います。
しかし、いざ認知症の方をケアしようと思うとなかなか大変で忍耐がいりますね。

次回は、認知症ケアの方法について、お話をしたいと思います。
そして、クリスティーン・ブライライデンさんについては、ネットで検索すれば本やDVDの情報が得られますので、興味ある方は、検索をしてください。

2018年11月13日
認知症について考えてみよう ~高次脳機能障害~
前回の若年性認知症を紹介したなかで、若年性認知症を起こす原因として、事故による頭部外傷後遺症が記載してありました。
この事故による頭部外傷後遺症による症状については、一般的に高次脳機能障害と言われております。
もちろん認知症のようなもの忘れ(記憶障害)の症状も現れてきます。
この高次脳機能障害は、脳卒中や交通事故が原因で、脳の機能のうち言語や記憶、注意、情緒といった認知機能に起こる障害を高次脳機能障害と言われております。
高次脳機能障害には、以下の症状が出ていきます。
☆記憶障害
*物の置き場所を忘れる。
*新しいできごとを覚えられない。
*同じことを繰り返し質問する。
☆注意障害
*ぼんやりしていて、ミスが多い。
*二つのことを同時に行うと混乱する。
*作業を長く続けられない。
☆遂行機能障害
*自分で計画を立ててものごとを実行することができない。
*人に指示してもらわないと何もできない。
*約束の時間に間に合わない
☆社会的行動障害
*興奮する暴力を振るう。
*思い道りならないと、大声をだす。
*自己中心的になる。
以上の症状により日常生活または社会生活に制約が起きます。
また、高次脳機能障害は外見からはわかりにくく、病院や診察では気づかれずに、実際の生活や社会日常生活に戻って初めて問題が顕在化(症状が出てくる)することがすくなく「見えない障害、隠れた障害」などとも言われております。
ですから、交通事後で入院し、退院後職場復帰したときに、今まで行っていた仕事の手順を思い出すことができない。
職場の人たちは、外見から分かりにくいので、ちぐはぐな事をしている本人の行動に理解できないー。
それが続くと、本人と職場の人たちに不協和音が出てきて、結果退職しなければならない。
ということがしばしばあるようです。
ですから、脳卒中や交通事故で東部外傷しないように、健康な生活や安全運転(特にバイクに乗る人は気をつけてください。)に気をつけることが大切です。
なお、高次脳機能障害につきましては、静岡県内にもサポートする団体もあるようなので、ネットで検索してみてください。
今回は、高次脳機能障害を紹介しましたが、私達身近に起こりうることなので、ぜひ参考にして下さい。
この事故による頭部外傷後遺症による症状については、一般的に高次脳機能障害と言われております。
もちろん認知症のようなもの忘れ(記憶障害)の症状も現れてきます。
この高次脳機能障害は、脳卒中や交通事故が原因で、脳の機能のうち言語や記憶、注意、情緒といった認知機能に起こる障害を高次脳機能障害と言われております。
高次脳機能障害には、以下の症状が出ていきます。
☆記憶障害
*物の置き場所を忘れる。
*新しいできごとを覚えられない。
*同じことを繰り返し質問する。
☆注意障害
*ぼんやりしていて、ミスが多い。
*二つのことを同時に行うと混乱する。
*作業を長く続けられない。
☆遂行機能障害
*自分で計画を立ててものごとを実行することができない。
*人に指示してもらわないと何もできない。
*約束の時間に間に合わない
☆社会的行動障害
*興奮する暴力を振るう。
*思い道りならないと、大声をだす。
*自己中心的になる。
以上の症状により日常生活または社会生活に制約が起きます。
また、高次脳機能障害は外見からはわかりにくく、病院や診察では気づかれずに、実際の生活や社会日常生活に戻って初めて問題が顕在化(症状が出てくる)することがすくなく「見えない障害、隠れた障害」などとも言われております。
ですから、交通事後で入院し、退院後職場復帰したときに、今まで行っていた仕事の手順を思い出すことができない。
職場の人たちは、外見から分かりにくいので、ちぐはぐな事をしている本人の行動に理解できないー。

それが続くと、本人と職場の人たちに不協和音が出てきて、結果退職しなければならない。

ということがしばしばあるようです。
ですから、脳卒中や交通事故で東部外傷しないように、健康な生活や安全運転(特にバイクに乗る人は気をつけてください。)に気をつけることが大切です。

なお、高次脳機能障害につきましては、静岡県内にもサポートする団体もあるようなので、ネットで検索してみてください。
今回は、高次脳機能障害を紹介しましたが、私達身近に起こりうることなので、ぜひ参考にして下さい。

2018年11月09日
認知症について考えてみよう ~若年性認知症~
実は、若い人でも認知症になると言われております。
若い人とは、どんな年齢って、思いますよねー
『若年性認知症』は、65歳未満に発症する認知症のことを言います。
若年性認知症の好発年齢は、40~60歳の働きざかりです。
男女比は、男性の方が多く、病気の進行も早いのが特徴とされております。
原因は、アルツハイマー型認知症と脳血管性認知症の2つで6割をしめ、前頭側頭型認知症(ピック病)、アルコール性認知症(アルコールの多量飲酒による脳の萎縮)事故なので頭部外傷後遺症などがあります。
アルツハイマー型認知症は、老廃物のタンパク質(ベータ・アミロイド)が脳にたまり、脳が萎縮する認知症ですが、遺伝によるケースもあり、その場合、発症年齢は30~50歳くらいと言われております。
初期は、頭痛やめまい、不眠が見られます、さらに不安感、自発性の低下、抑うつ状態となり、うつ病と間違えられるケースもあるようです。
以前に比べて、頑固で、自分中心となり、他人への配慮がなくなったと感じたら要注意!!
ひどいもの忘れや、帰宅中で迷子になるようなことがあれば、赤信号です。
次に脳血管性認知症の認知症は、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞等で脳の血流が障害され起こり、これらの発作によって意識の低下、睡眠障害、麻痺、言語障害などの症状が現れます。
発作が治まった後も麻痺や言語障害などが残る他、意欲低下、記憶障害、注意力や集中力の低下など症状が現れ、日常生活に支障を及ぼすようになります。
前頭側頭型認知症(ピック病)は、「仕事ぶりがずさんになった」「約束を破る」など人格の変化がポイントになります。
不潔になったり、衣類の乱れを気にしなくなることも。アルツハイマー病に似ているが、違うのは行動上の異変が目立つ、不安感情が見られないなどの点。このほか「話しかけられた言葉を何度のくりかえる」「言葉を一切話せなくなる」などの言語障害も危険信号となります。
若年性認知症は、働きざかりで家族を養う大事な時期に発症するので、なっといっても早期発見が大切です。
「忘れっぽくなった」「同じ物を買ってくる」「仕事の段取りが遅くなる」「失敗が増える」「やる気が起きない」などと感じたら受診をお勧めします。
早めに治療に入ることで、症状の進行を遅らせたり、生活の改善が図ることが可能となります。
また、自分の病気を知り、今後の生活や仕事への準備ができます。
この若年性認知症が示すように認知症は65歳以上の高齢者の病気ではありません。
40歳を過ぎたら、生活習慣を見直すことも認知症の予防につながりますので、該当する方は、生活習慣病にならないように過ごすことも大事です。
以上、若年性認知症を紹介しました。
若い人とは、どんな年齢って、思いますよねー
『若年性認知症』は、65歳未満に発症する認知症のことを言います。
若年性認知症の好発年齢は、40~60歳の働きざかりです。
男女比は、男性の方が多く、病気の進行も早いのが特徴とされております。
原因は、アルツハイマー型認知症と脳血管性認知症の2つで6割をしめ、前頭側頭型認知症(ピック病)、アルコール性認知症(アルコールの多量飲酒による脳の萎縮)事故なので頭部外傷後遺症などがあります。
アルツハイマー型認知症は、老廃物のタンパク質(ベータ・アミロイド)が脳にたまり、脳が萎縮する認知症ですが、遺伝によるケースもあり、その場合、発症年齢は30~50歳くらいと言われております。
初期は、頭痛やめまい、不眠が見られます、さらに不安感、自発性の低下、抑うつ状態となり、うつ病と間違えられるケースもあるようです。
以前に比べて、頑固で、自分中心となり、他人への配慮がなくなったと感じたら要注意!!
ひどいもの忘れや、帰宅中で迷子になるようなことがあれば、赤信号です。
次に脳血管性認知症の認知症は、脳出血、くも膜下出血、脳梗塞等で脳の血流が障害され起こり、これらの発作によって意識の低下、睡眠障害、麻痺、言語障害などの症状が現れます。
発作が治まった後も麻痺や言語障害などが残る他、意欲低下、記憶障害、注意力や集中力の低下など症状が現れ、日常生活に支障を及ぼすようになります。
前頭側頭型認知症(ピック病)は、「仕事ぶりがずさんになった」「約束を破る」など人格の変化がポイントになります。
不潔になったり、衣類の乱れを気にしなくなることも。アルツハイマー病に似ているが、違うのは行動上の異変が目立つ、不安感情が見られないなどの点。このほか「話しかけられた言葉を何度のくりかえる」「言葉を一切話せなくなる」などの言語障害も危険信号となります。
若年性認知症は、働きざかりで家族を養う大事な時期に発症するので、なっといっても早期発見が大切です。
「忘れっぽくなった」「同じ物を買ってくる」「仕事の段取りが遅くなる」「失敗が増える」「やる気が起きない」などと感じたら受診をお勧めします。
早めに治療に入ることで、症状の進行を遅らせたり、生活の改善が図ることが可能となります。
また、自分の病気を知り、今後の生活や仕事への準備ができます。
この若年性認知症が示すように認知症は65歳以上の高齢者の病気ではありません。
40歳を過ぎたら、生活習慣を見直すことも認知症の予防につながりますので、該当する方は、生活習慣病にならないように過ごすことも大事です。
以上、若年性認知症を紹介しました。

2018年11月06日
H30.11.7~H30.11.20までの営業のお知らせ
ケアマネージャーの仕事の都合により、営業時間を変更させていただきます。(H30.11.7-H30.11.20)
11月 9日(金) 9:00~12:00 14:00~16:00
11月12日(月) 9:00~12:00 14:00~19:00
11月16日(金) 午前休診 14:00~19:00
11月20日(月) 9:00~12:00 14:00~19:00
上記の以外の期間内営業(H30.11.7-H30.11.20)については、日曜日を除いて、18:30以降に電話があったときに対応させていただきます。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご協力をお願いします。

2018年11月02日
松屋でうまトマハンバーグ定食を食べてみました。
静岡市産学交流セミナー(平成30年10月25日)終了後、松屋に立ち寄り夕食を食べました。
今回注文したのは、うまトマハンバーグ定食です。

写真で見たとおりに、半熟玉子にトマトとハンバーグ、その上にトマトとチリソースが合わさった酸味と辛味のあるソースがかかっております。
この半熟玉子とハンバーグにかかっているソースをごはんにかけると美味しい。

ハンバーグも酸味と辛味の混ざったソースがかかっているので、スバイシィーで美味しかったです。
また、来店したいと思います。



