2009年06月19日
人間は左右非対称の動物である。
テレビで美容番組を見ていると、顔の半分にさくを入れて写真を撮影すると、顔が左右非対称に写って出てくることがあります。
また、普段は気づきませんが、自分の姿全体を鏡でよく見てみると、左右の肩の高さが違うことに気づきます。
これらは、生活習慣(字を書く姿勢、食事の姿勢、仕事をしている時の姿勢、電車の座イスに座っている姿勢など)が原因だと思われます。
私達は、気づかない内に生活習慣に慣れた姿勢をしており、この姿勢を維持するために、体がねじれてバランスをとっています。
当然バランスが崩れれば、筋肉でも緩む所もあれば、引っ張られて緊張するところが出てきます。そうなれば、両肩の高さが違ってきてもおかしくはありません。
左右で筋肉の緊張が違えば、筋肉の上にあり皮膚の部分にある“ツボ”に、影響が出ないはずがありせん!!
もちろん、左右同じ位置にあるツボの緊張も違ってきます。
実際に皆さんもやっていただくとわかるのですが、
例えば、両腕にある手三里(下の図を参照)というツボ。肘を曲げて外側を見ると、曲げた部分に深いしわができます。この部分は曲池(きょくち)というツボがあります。この曲池より指二本ぶん前に手三里というツボがあります。だいたいこのツボの周囲を押してみるとわかるのですが、左右のツボの緊張が違うことがわかります。


これは、体がねじれているからです。
つまり、治療ではこのねじれを修正する必要があります。
ですから、鍼治療(はりちりょう)では、両方に治療せずに、どちらか一方に治療を行い、体のバランスを取るようにします。
また、灸治療(きゅうちりょう)では左右同時にお灸行います。左右のバランスが崩れているときは、どちらか一方が熱く感じます。一般的に病んでいるツボは、お灸をしてもあまり熱く感じません。ですから、左右にお灸をして、両方とも同じ熱さに感じられるようになったときに、バランスが改善したと判定します。
以上が、私が治療を行うときのポイントとしている部分です。
そして、バランスという考えでいけば、病んでいる場所だけが悪いとは限りません。
別の場所が慢性化して病んでおり、あまり目立たない状態にあり、そこからバランスがくずれ、体がねじれて弱っている場所に症状が出現する場合もあります。
ですから、治療を行う場合は、苦しく感じる患部だけを診るのではなく、全身を診る必要があると思います。
また、普段は気づきませんが、自分の姿全体を鏡でよく見てみると、左右の肩の高さが違うことに気づきます。
これらは、生活習慣(字を書く姿勢、食事の姿勢、仕事をしている時の姿勢、電車の座イスに座っている姿勢など)が原因だと思われます。
私達は、気づかない内に生活習慣に慣れた姿勢をしており、この姿勢を維持するために、体がねじれてバランスをとっています。
当然バランスが崩れれば、筋肉でも緩む所もあれば、引っ張られて緊張するところが出てきます。そうなれば、両肩の高さが違ってきてもおかしくはありません。
左右で筋肉の緊張が違えば、筋肉の上にあり皮膚の部分にある“ツボ”に、影響が出ないはずがありせん!!
もちろん、左右同じ位置にあるツボの緊張も違ってきます。
実際に皆さんもやっていただくとわかるのですが、
例えば、両腕にある手三里(下の図を参照)というツボ。肘を曲げて外側を見ると、曲げた部分に深いしわができます。この部分は曲池(きょくち)というツボがあります。この曲池より指二本ぶん前に手三里というツボがあります。だいたいこのツボの周囲を押してみるとわかるのですが、左右のツボの緊張が違うことがわかります。


これは、体がねじれているからです。
つまり、治療ではこのねじれを修正する必要があります。
ですから、鍼治療(はりちりょう)では、両方に治療せずに、どちらか一方に治療を行い、体のバランスを取るようにします。
また、灸治療(きゅうちりょう)では左右同時にお灸行います。左右のバランスが崩れているときは、どちらか一方が熱く感じます。一般的に病んでいるツボは、お灸をしてもあまり熱く感じません。ですから、左右にお灸をして、両方とも同じ熱さに感じられるようになったときに、バランスが改善したと判定します。
以上が、私が治療を行うときのポイントとしている部分です。
そして、バランスという考えでいけば、病んでいる場所だけが悪いとは限りません。
別の場所が慢性化して病んでおり、あまり目立たない状態にあり、そこからバランスがくずれ、体がねじれて弱っている場所に症状が出現する場合もあります。
ですから、治療を行う場合は、苦しく感じる患部だけを診るのではなく、全身を診る必要があると思います。
2009年06月08日
弁証論治(べんしょうろんち)はPDCAサイクルに似ている。
現代のビジネスパーソンは、“自分で考え行動できる人”が必要とされていると言われいます。
これは、待ちの姿勢では、現代の社会の生存競争に勝ち残ることは、できないことを示してのでは
ないでしょうか。
でも、企画が立てて実行するだけでは、ダメである。結果と考察をしなければ、次に生きてくるもの
がないと思います。
物を作る生産現場では、生産管理や品質管理では、PDCAサイクルという手法が用いられています。
PDCAとは、それぞれの頭文字をとったもの
P(Plan:計画)、D(Do:実行・実施)、C(Check:点検・評価)、A(Action:改善) 物を作るときに、P⇒D⇒C⇒Aと進み、またPに戻るという。これは、より良い品質を作るための基本的な考え方です。
私が鍼灸治療(しんきゅうちりょう)で行っている弁証論治(べんしょうろんち)の考え方も、PDCAサイクルに似ていると思います。
P(Plan:診察を行い、証〔東洋医学的な診断]をたて、治療方針を決める)
▽
D(Do:治療方針に従って、治療を行う)
▽
C(Check:症状の軽減や体の変化〔顔色の変化、舌の色や形の変化、脈の変化の有無、お腹・背中のツボの変化など〕を確認する)
▽
A(Action:治療後の変化から、養生法と次の治療に生かす反省点を見つけ出す)

少し無理に押し込めた感じがありますが....
要は何を言いたいのかと言うと、この世に万能のツボや治療法は存在はしません。 しっかりと治療計画をたて、それをまず実行する。そして、結果を把握し、次にどんな養生や治療をしたら良いか考える。
この一連のサイクルがあって始めて、確実で治療効果のある治療が行えるのです。それには、何が効果があるかしっかりと確認しなければいけない。そうなると1本の鍼(はり)が体にどう影響しているのかを追う必要がでます。
そうして、確実に効果が出る鍼灸治療(しんきゅうちりょう)が行われると思います。
これは、待ちの姿勢では、現代の社会の生存競争に勝ち残ることは、できないことを示してのでは
ないでしょうか。
でも、企画が立てて実行するだけでは、ダメである。結果と考察をしなければ、次に生きてくるもの
がないと思います。
物を作る生産現場では、生産管理や品質管理では、PDCAサイクルという手法が用いられています。
PDCAとは、それぞれの頭文字をとったもの
P(Plan:計画)、D(Do:実行・実施)、C(Check:点検・評価)、A(Action:改善) 物を作るときに、P⇒D⇒C⇒Aと進み、またPに戻るという。これは、より良い品質を作るための基本的な考え方です。
私が鍼灸治療(しんきゅうちりょう)で行っている弁証論治(べんしょうろんち)の考え方も、PDCAサイクルに似ていると思います。
P(Plan:診察を行い、証〔東洋医学的な診断]をたて、治療方針を決める)
▽
D(Do:治療方針に従って、治療を行う)
▽
C(Check:症状の軽減や体の変化〔顔色の変化、舌の色や形の変化、脈の変化の有無、お腹・背中のツボの変化など〕を確認する)
▽
A(Action:治療後の変化から、養生法と次の治療に生かす反省点を見つけ出す)

少し無理に押し込めた感じがありますが....
要は何を言いたいのかと言うと、この世に万能のツボや治療法は存在はしません。 しっかりと治療計画をたて、それをまず実行する。そして、結果を把握し、次にどんな養生や治療をしたら良いか考える。
この一連のサイクルがあって始めて、確実で治療効果のある治療が行えるのです。それには、何が効果があるかしっかりと確認しなければいけない。そうなると1本の鍼(はり)が体にどう影響しているのかを追う必要がでます。
そうして、確実に効果が出る鍼灸治療(しんきゅうちりょう)が行われると思います。
2009年06月05日
少ないハリで、さまざまな症状が改善するメカニズム
皆さん、いきなりクイズです。
さて、1~3本の鍼(はり)を使って、患者さん訴えるさまざまな症状を治療するにはどのようにしたらよいのでしょうか?
ちなみに、これはマジックではありません。
その答えは、患者さんの訴える症状を“病気の型”として分類して、これに合う治療を行えば、少ない鍼(はり)で、治すことができます。
東洋医学では、この“病気の型”は『証(しょう)』と言います。西洋医学で言うと『診断名』に当たります。
そして、診断名である『証』を見つけ出すには、西洋医学に当たる診察・検査が必要になってきます。
それに当たるのが、問診(もんしん⇒患者さんの訴えや生活状況をきく)・舌診(ぜっしん⇒舌の色や形をみる)・脈診(みゃくしん⇒みゃくの硬さや速さをみる)・腹診(ふくしん⇒内臓に近いお腹のツボの反応をみる)・背候診(はいこうしん⇒内臓に近い背中のツボの反応をみる、背中の筋肉のバランスをみる)・手足にあるツボの反応をみる原穴診(げんけつしん⇒ケイラク《ツボの流れ》の状態をみる)です。
以上の診察で得た情報から、東洋医学4千年の経験から考えられた“病気の型”、つまり『証』を引き出すのです。
そして、『証』に合った治療方法を行うのです。東洋医学では、このことを『弁証論治(べんしょうろんち)』と言います。
内容的には、西洋医学と同じです。『患者さんが訴えている症状に対して、悪い場所を見つけて、そこを集中的に治療を行うこと』とほとんどかわりません。
違うといえば、経験が重視されるので、何がこの“病気の形”に効果があったのか、はっきりさせる必要があります。
ここで、たくさんのツボに鍼灸治療(しんきゅうちりょう)を行うと“どのツボが効果があった”のか、わからなくなってしまいます。
ですから、少ないツボを刺激して効果を判断する必要性が出てきます。これが、少ない鍼(はり)で治療を行う理由になります。
“病気の型”つまり『証』を使った治療は、先人が作った経験を元に考えだされています。そして、少ない鍼(はり)は、身体に負担をかけなく、主に手足・お腹・背中に治療を行うので、安全性が高い方法です。
これからも、「この治療方法の素晴らしさを皆さんに伝えていけたら良いかな」と思っています。
さて、1~3本の鍼(はり)を使って、患者さん訴えるさまざまな症状を治療するにはどのようにしたらよいのでしょうか?
ちなみに、これはマジックではありません。
その答えは、患者さんの訴える症状を“病気の型”として分類して、これに合う治療を行えば、少ない鍼(はり)で、治すことができます。
東洋医学では、この“病気の型”は『証(しょう)』と言います。西洋医学で言うと『診断名』に当たります。
そして、診断名である『証』を見つけ出すには、西洋医学に当たる診察・検査が必要になってきます。
それに当たるのが、問診(もんしん⇒患者さんの訴えや生活状況をきく)・舌診(ぜっしん⇒舌の色や形をみる)・脈診(みゃくしん⇒みゃくの硬さや速さをみる)・腹診(ふくしん⇒内臓に近いお腹のツボの反応をみる)・背候診(はいこうしん⇒内臓に近い背中のツボの反応をみる、背中の筋肉のバランスをみる)・手足にあるツボの反応をみる原穴診(げんけつしん⇒ケイラク《ツボの流れ》の状態をみる)です。
以上の診察で得た情報から、東洋医学4千年の経験から考えられた“病気の型”、つまり『証』を引き出すのです。
そして、『証』に合った治療方法を行うのです。東洋医学では、このことを『弁証論治(べんしょうろんち)』と言います。
内容的には、西洋医学と同じです。『患者さんが訴えている症状に対して、悪い場所を見つけて、そこを集中的に治療を行うこと』とほとんどかわりません。
違うといえば、経験が重視されるので、何がこの“病気の形”に効果があったのか、はっきりさせる必要があります。
ここで、たくさんのツボに鍼灸治療(しんきゅうちりょう)を行うと“どのツボが効果があった”のか、わからなくなってしまいます。
ですから、少ないツボを刺激して効果を判断する必要性が出てきます。これが、少ない鍼(はり)で治療を行う理由になります。
“病気の型”つまり『証』を使った治療は、先人が作った経験を元に考えだされています。そして、少ない鍼(はり)は、身体に負担をかけなく、主に手足・お腹・背中に治療を行うので、安全性が高い方法です。
これからも、「この治療方法の素晴らしさを皆さんに伝えていけたら良いかな」と思っています。
2009年05月25日
ツボにはまればハリは痛くない!!
よく鍼灸院(しんきゅういん)のホームページを見ていると“ハリは痛くありません”と掲載されています。
でも、見た人の大半がハリを刺すんだから全く痛くないということはあり得ないと思うはずです。
結論からいえば、「刺すはり全て痛くない」ということはありません。
しかし、“ツボにしっかり入った時(患者さんは、この場所は気持ちがよくて、効く感じがすると実感する時)は、全く痛みを感じない”ようです。
逆にはりを刺したときにあまりに痛い場合は、“ツボに入っていない時”と思ったほうがいいです。
その他に、ハリをすることに緊張してしまう方もいらっしゃいます。
当院では、そんな方の為に、はり刺入時の痛みや緊張の緩和に呼吸法を用いています。
具体的には“最初に息を吸っていただき、その後息をゆっくり入っていただいている間にハリを刺入します。”この方法ですと、患者さんが息をはいていることに夢中になっているときにハリを刺入しますので、痛みを感じることが少なくなります。
また、ハリに恐怖感を持っている方、神経が過敏な方や小児に、カラダの中に刺さずに皮膚の表面を刺激するだけで効果がでるハリ(古代鍼といいます。下の写真を見てください。)を使用する場合があります。
このハリは、極端に過敏に反応する方に有効です!!
普通の方は、普通の刺すハリのほうが効果が出やすいように感じます。
当院では、これらのハリを用いて、その方の感じ方や体の状態を診てハリ治療をしていきます。
ですから“ハリ治療を受けたいが、恐い”と感じる方も安心して治療を受けていただきたいと思います。

古代鍼(こだいしん)
でも、見た人の大半がハリを刺すんだから全く痛くないということはあり得ないと思うはずです。
結論からいえば、「刺すはり全て痛くない」ということはありません。
しかし、“ツボにしっかり入った時(患者さんは、この場所は気持ちがよくて、効く感じがすると実感する時)は、全く痛みを感じない”ようです。
逆にはりを刺したときにあまりに痛い場合は、“ツボに入っていない時”と思ったほうがいいです。
その他に、ハリをすることに緊張してしまう方もいらっしゃいます。
当院では、そんな方の為に、はり刺入時の痛みや緊張の緩和に呼吸法を用いています。
具体的には“最初に息を吸っていただき、その後息をゆっくり入っていただいている間にハリを刺入します。”この方法ですと、患者さんが息をはいていることに夢中になっているときにハリを刺入しますので、痛みを感じることが少なくなります。
また、ハリに恐怖感を持っている方、神経が過敏な方や小児に、カラダの中に刺さずに皮膚の表面を刺激するだけで効果がでるハリ(古代鍼といいます。下の写真を見てください。)を使用する場合があります。
このハリは、極端に過敏に反応する方に有効です!!
普通の方は、普通の刺すハリのほうが効果が出やすいように感じます。
当院では、これらのハリを用いて、その方の感じ方や体の状態を診てハリ治療をしていきます。
ですから“ハリ治療を受けたいが、恐い”と感じる方も安心して治療を受けていただきたいと思います。

古代鍼(こだいしん)
2009年05月15日
現在の治療法との出会い③(奇跡を起こした治療に出会った編)
私の勉強していた麻酔科では、研修生の先輩たちが、入院患者のお世話をしていました。仕事の内容は、日中の患者さんとの運動と鍼灸治療(しんきゅうちりょう)を行っていました。
鍼灸治療は、他の科のように西洋医学の解剖や生理を根拠した治療法でなく、中医学(中国伝統医学)をベースにした治療を行っていました。おそらく、病院内で一番東洋医学的な治療ができた科だったと思います。
かの私も麻酔科に入って、先輩から強制的に中医学を勉強させられました。そして、現在の治療法に出会ったのでした。
最初にこの治療に出会ったときに、“正直こんな少ない鍼で治るの?”と半信半疑の状態でしたので、なかなか科に馴染めない状態でした。その状況を見ていた先輩からよく絞られました。仕方なしに、難解な中医学の勉強をしだして、半年がたった時に転機が訪れました。
20年以上の不眠症の患者さんが麻酔科に入院してきました。私が始めて担当した患者さんです。睡眠薬が全く効かない人で、治療はテンプレート・漢方薬・運動・鍼灸治療を行いました。しかし、実際は漢方薬もあまり使わず、治療のほとんどは鍼灸治療でした。
私は、この患者さんに手の合谷(ごうこく)と足の太衝(たいしょう)の2つのツボで治療を行い、約2ヶ月間ほぼ毎日治療を行った結果、不眠症が改善したのです。

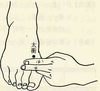
後から考えれば、入院しているから規則正しい生活をしており、それに加えて日中運動しているので、夜間眠りに入
りやすい状態でした。
でも、“この時初めて不眠症を治したこと、しかも20年も苦しんだものをたった2つのツボで治した。”と自分の中で興奮し、この時初めて鍼灸治療のすごさを感じました。
この感激に味をしめてしまった私は、徐々にこの少ない鍼治療(はりちりょう)にのめり込んでいきました。
鍼灸治療は、他の科のように西洋医学の解剖や生理を根拠した治療法でなく、中医学(中国伝統医学)をベースにした治療を行っていました。おそらく、病院内で一番東洋医学的な治療ができた科だったと思います。
かの私も麻酔科に入って、先輩から強制的に中医学を勉強させられました。そして、現在の治療法に出会ったのでした。
最初にこの治療に出会ったときに、“正直こんな少ない鍼で治るの?”と半信半疑の状態でしたので、なかなか科に馴染めない状態でした。その状況を見ていた先輩からよく絞られました。仕方なしに、難解な中医学の勉強をしだして、半年がたった時に転機が訪れました。
20年以上の不眠症の患者さんが麻酔科に入院してきました。私が始めて担当した患者さんです。睡眠薬が全く効かない人で、治療はテンプレート・漢方薬・運動・鍼灸治療を行いました。しかし、実際は漢方薬もあまり使わず、治療のほとんどは鍼灸治療でした。
私は、この患者さんに手の合谷(ごうこく)と足の太衝(たいしょう)の2つのツボで治療を行い、約2ヶ月間ほぼ毎日治療を行った結果、不眠症が改善したのです。

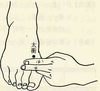
後から考えれば、入院しているから規則正しい生活をしており、それに加えて日中運動しているので、夜間眠りに入
りやすい状態でした。
でも、“この時初めて不眠症を治したこと、しかも20年も苦しんだものをたった2つのツボで治した。”と自分の中で興奮し、この時初めて鍼灸治療のすごさを感じました。
この感激に味をしめてしまった私は、徐々にこの少ない鍼治療(はりちりょう)にのめり込んでいきました。
2009年05月11日
現在の治療法との出会い②(麻酔科って、どんな科編)
皆さんは、麻酔科と聞いてどんなことを連想されますか?
病院に行かれて『麻酔科・ペインクリニック』という看板を見たことがあるの思います。ペインクリニックとは、痛みのきつい患者さんに対して、麻酔薬入った注射器で神経の働きを鈍くする神経ブロックなどを思い浮かべると思います。その他には、手術の時の全身麻酔を担当し、同時に呼吸管理も行っています。
現在医師不足が言われてますが、麻酔科の医師不足の影響で、思うように手術が日程どうりに行えない事態になっているそうです。これは、世間から麻酔科の医師がどんな仕事をしているのか認識されていない為、麻酔科を選択する医師にも影響を与えているのだと私は考えています。
さて、自分の話しに戻りたいと思います。
私が麻酔科に入った時の指導教官の医師がとても変わった人でした。何がかわっているのかというと、“西洋医学より民間療法の方がすぐれている”と考えていたからです。これは、先生が外科医時代に身内を癌で亡くされたれた経験があり、西洋医学では癌は救えなかったという経験から民間療法の“奇跡”に着目したと考えられます。
普通民間医療に目覚めたといいても、医師の場合は外来で試す程度なのですが、この先生は入院患者さんをとって民間療法を行っていました。麻酔科医が入院患者を持つことは、その当時はありませんでした。なぜなら、手術に立ち会うといっても、患者さんは外科系の診療科に入院するからです。
入院患者さんがいないということは、自分の時間が取れるのです。先生はその時間を使って、民間療法の検証していて、当時は歯科医の先生とタックを組んで“テンプレート療法”を行っていました。
“テンプレート療法”とは、マウスピースを使った治療法のことです。理論を簡単に説明すると、歯のかみ合わせが悪いと首の骨の並びが悪くなり、その周囲の筋肉バランスが崩れて神経にも影響を及ぼし、やがて全身に影響するというものです。
治療法は、最初に患者のかみ合わせをチェックを行い、次に歯に入れるマウスピースの高さを調整し、左右の顎の関節が水平になるようにする。つまり、かみ合わせが良ければ、全身の不快な症状も軽減するという考えでした。
この“テンプレート療法”加えて、入院患者さんを病院の中から連れ出して、散歩や鍼灸治療を行っており、病院のなかでも怪しい科に見えていました。
私はそこで勉強するのがイヤだったのですが、尊敬する耳鼻科の先生に言われたことと、病院研修後について考えて臨床をたくさん経験したほうが良いと思い、麻酔科で勉強することを決めました。
注:“テンプレート療法”は、立派な治療法です。私は、どちらかと言うと鍼灸がメインにならないと気がすまないのです。して、“テンプレート療法”を否定するものではありません。
なお、“テンプレート療法”に興味がある方は、お気に入りのとこに掲載されている「NPO日本テンプレート研究会」にアクセスしてください。
病院に行かれて『麻酔科・ペインクリニック』という看板を見たことがあるの思います。ペインクリニックとは、痛みのきつい患者さんに対して、麻酔薬入った注射器で神経の働きを鈍くする神経ブロックなどを思い浮かべると思います。その他には、手術の時の全身麻酔を担当し、同時に呼吸管理も行っています。
現在医師不足が言われてますが、麻酔科の医師不足の影響で、思うように手術が日程どうりに行えない事態になっているそうです。これは、世間から麻酔科の医師がどんな仕事をしているのか認識されていない為、麻酔科を選択する医師にも影響を与えているのだと私は考えています。
さて、自分の話しに戻りたいと思います。
私が麻酔科に入った時の指導教官の医師がとても変わった人でした。何がかわっているのかというと、“西洋医学より民間療法の方がすぐれている”と考えていたからです。これは、先生が外科医時代に身内を癌で亡くされたれた経験があり、西洋医学では癌は救えなかったという経験から民間療法の“奇跡”に着目したと考えられます。
普通民間医療に目覚めたといいても、医師の場合は外来で試す程度なのですが、この先生は入院患者さんをとって民間療法を行っていました。麻酔科医が入院患者を持つことは、その当時はありませんでした。なぜなら、手術に立ち会うといっても、患者さんは外科系の診療科に入院するからです。
入院患者さんがいないということは、自分の時間が取れるのです。先生はその時間を使って、民間療法の検証していて、当時は歯科医の先生とタックを組んで“テンプレート療法”を行っていました。
“テンプレート療法”とは、マウスピースを使った治療法のことです。理論を簡単に説明すると、歯のかみ合わせが悪いと首の骨の並びが悪くなり、その周囲の筋肉バランスが崩れて神経にも影響を及ぼし、やがて全身に影響するというものです。
治療法は、最初に患者のかみ合わせをチェックを行い、次に歯に入れるマウスピースの高さを調整し、左右の顎の関節が水平になるようにする。つまり、かみ合わせが良ければ、全身の不快な症状も軽減するという考えでした。
この“テンプレート療法”加えて、入院患者さんを病院の中から連れ出して、散歩や鍼灸治療を行っており、病院のなかでも怪しい科に見えていました。
私はそこで勉強するのがイヤだったのですが、尊敬する耳鼻科の先生に言われたことと、病院研修後について考えて臨床をたくさん経験したほうが良いと思い、麻酔科で勉強することを決めました。
注:“テンプレート療法”は、立派な治療法です。私は、どちらかと言うと鍼灸がメインにならないと気がすまないのです。して、“テンプレート療法”を否定するものではありません。
なお、“テンプレート療法”に興味がある方は、お気に入りのとこに掲載されている「NPO日本テンプレート研究会」にアクセスしてください。
2009年05月10日
現在の治療法との出会い①(出会いまでの道のり編)
私の鍼治療(はりちりょう)は、少ない本数(1から多くて5本)で治療を行います。『治療を受けた人からは、これで良くなるの?』と言われることがあります。また、良くなかった方から数本の鍼治療で良くなったのが信じられず『注射を打ってもらった』と言われる人があります。
もっとも私は、注射を打つ医療の免許はありませんので、あくまでも鍼(はり)やお灸(おきゅう)で、身体を刺激して症状を改善しているだけです。
私も初心者の頃は、皆さんが知っている鍼治療(主に痛い所に治療をするやり方)をしており、鍼をたくさん打っていました。そんな自分がどうして、治療方法を変えたのか。皆さんに紹介したいと思います。
私は高校を卒業してから、その当時日本で一つしかない鍼灸の大学であった明治鍼灸大学(現:明治国際医療大学)に進学しました。当時の明治鍼灸大学は、日本で唯一の鍼灸大学であると同時に鍼灸の学校として唯一附属病院を持っていました。
新しい学校だったので、鍼灸をいかに医療として認められるのか、学校全体で模索していました。まだ、その時は大学院もない時代(現在は、大学院博士過程まである。)だったので、卒後鍼灸界をリードしていく人材が養成したいと考え、病院で勉強してもらう研修制度がありました。
私も「病院で鍼灸治療の可能性をしりたい。」と思い、卒業後は研修生として附属の病院で、勉強させていただきました。この研修制度は、医師の研修制度と一緒で、指導教官が医師であり、金魚のフンみたいな感じで、病院内を医師の後を歩いていたのを思い出します。
1年目は、各科(脳神経外科、外科、内科、麻酔科、泌尿器科、眼科、歯科、整形外科、耳鼻科)をローテッションで周り、2年目は自分の希望する科で勉強することになっていました。当初私は、子供の鍼灸治療に興味をもち、アレルギーのことを勉強できる耳鼻科を選択するつもりでした。
でも、その時に教授である指導教官の医師がアメリカに留学することとなり、その先生から「きみは、もっと臨床が出来る科にいった方がよい。」と勧められ、一番行きたくなっかた麻酔科で、しぶしぶ研修することになり、その時に現在の治療法に出会ったのです。
もっとも私は、注射を打つ医療の免許はありませんので、あくまでも鍼(はり)やお灸(おきゅう)で、身体を刺激して症状を改善しているだけです。
私も初心者の頃は、皆さんが知っている鍼治療(主に痛い所に治療をするやり方)をしており、鍼をたくさん打っていました。そんな自分がどうして、治療方法を変えたのか。皆さんに紹介したいと思います。
私は高校を卒業してから、その当時日本で一つしかない鍼灸の大学であった明治鍼灸大学(現:明治国際医療大学)に進学しました。当時の明治鍼灸大学は、日本で唯一の鍼灸大学であると同時に鍼灸の学校として唯一附属病院を持っていました。
新しい学校だったので、鍼灸をいかに医療として認められるのか、学校全体で模索していました。まだ、その時は大学院もない時代(現在は、大学院博士過程まである。)だったので、卒後鍼灸界をリードしていく人材が養成したいと考え、病院で勉強してもらう研修制度がありました。
私も「病院で鍼灸治療の可能性をしりたい。」と思い、卒業後は研修生として附属の病院で、勉強させていただきました。この研修制度は、医師の研修制度と一緒で、指導教官が医師であり、金魚のフンみたいな感じで、病院内を医師の後を歩いていたのを思い出します。
1年目は、各科(脳神経外科、外科、内科、麻酔科、泌尿器科、眼科、歯科、整形外科、耳鼻科)をローテッションで周り、2年目は自分の希望する科で勉強することになっていました。当初私は、子供の鍼灸治療に興味をもち、アレルギーのことを勉強できる耳鼻科を選択するつもりでした。
でも、その時に教授である指導教官の医師がアメリカに留学することとなり、その先生から「きみは、もっと臨床が出来る科にいった方がよい。」と勧められ、一番行きたくなっかた麻酔科で、しぶしぶ研修することになり、その時に現在の治療法に出会ったのです。


