2014年11月28日
平成26年12月の休診のお知らせ
◇◆◇平成26年12月の休診のおしらせ◇◆◇
◎12月3日(水)は研修の為、午後の施術を5時までとさせていただきます。
◎12月15日(月)は研修の為、午後の施術を休診とさせていただきます。
*今年は、12月26日(土)まで営業を行います。
以上間違えないようにお願いします。
◎12月3日(水)は研修の為、午後の施術を5時までとさせていただきます。
◎12月15日(月)は研修の為、午後の施術を休診とさせていただきます。
*今年は、12月26日(土)まで営業を行います。
以上間違えないようにお願いします。
2014年11月25日
杵屋でうめわかめうどんを食べてみました。
先週の木曜日(平成26年11月20日)浜松にて研修会が行われ、行ってきました。
その時に、駅ビルMAYONEの横にあります杵屋(きねや)さんに立ち寄って、昼食をたべました。
このお店は、手打ちうどんのお店であります。
店内に入ると、職人さんがうどんを手打ちにして作っている風景が見えるお店であります。
私が注文したのは、梅わかめうんどんです。
半玉うどん無料ということなので、半玉増量をお願いしました。
しばらくすると、注文したうどんが出てきました。

さっそく食してみると、うどんは手打ちなので、歯ごたえがよく、つゆもダシが効いておいしい。
紀州の大きい梅を少しかじりながら、うどんを食べるとまた違った味で、楽しめます。
値段も良心的なお店なので、また浜松に着た時には、寄らしていただきまーす。
その時に、駅ビルMAYONEの横にあります杵屋(きねや)さんに立ち寄って、昼食をたべました。
このお店は、手打ちうどんのお店であります。
店内に入ると、職人さんがうどんを手打ちにして作っている風景が見えるお店であります。
私が注文したのは、梅わかめうんどんです。
半玉うどん無料ということなので、半玉増量をお願いしました。
しばらくすると、注文したうどんが出てきました。

さっそく食してみると、うどんは手打ちなので、歯ごたえがよく、つゆもダシが効いておいしい。

紀州の大きい梅を少しかじりながら、うどんを食べるとまた違った味で、楽しめます。
値段も良心的なお店なので、また浜松に着た時には、寄らしていただきまーす。

2014年11月22日
松屋 豚バラ焼肉定食を食べてみました。
B-nest(静岡市産学交流センター)のセミナーに参加した後、夕食を食べるために、松屋に立ち寄りました。
当日はとても寒く、席に座った時に出されたお茶があったかくておいしかった。
これほど、お茶がおいしく感じられるには、久しぶりです。

さて、今回は豚バラ焼肉定食を注文しました。
しばらくして、注文したものを見てみると、サラダに入ったお皿が大きかったせいか、ボリュウムがある定食に思えました。

さっそく、食してみると、胡椒のかかった豚肉は薄くて脂っこいのですが、ダイコンおろしのポン酢を付けてあっさりしていました。
サラダは結構ボリュームがあり、これで550円とはお得感があるのではないでしょうか。

また、来店したいと思います。

2014年11月18日
『「小っちゃな」会社が大きな会社に負けないためのマーケティング戦略
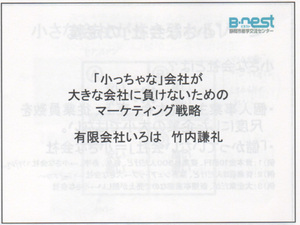
先週の金曜日(平成26年11月14日)にB-nest(静岡市産学交流センター)のセミナーがペガサートにて開催され、行って来ました。
今回は『「小っちゃな」会社が大きな会社に負けないためのマーケティング戦略』と題して、コンサルタントの竹内謙礼氏が講演されました。
またこの講演は、竹内氏の近著『小さい会社こそ高く売りなさい』の内容からのお話しでした。
竹内氏がこの本を書いた理由は、小さな会社が有名なマーケティング戦略を適応しても、なかなか成果がでないのではどうしてか?
それを突き詰めたのが本を書いた理由をだそうです。
まず「小さな会社」が「大きな会社」に勝てない理由は、「お金(資本力がない)」と「時間(余裕がない)」と「人(問題を解決する人材がない)」等。
それでは、別に「大きな会社」と戦わなくてもいいのでは?
・販売チャンネルがボーダレス化として小さな会社が浸食されている。
・新規顧客が急激に減っている。常連客が急激に高齢化している。
・商品力よりも「価格競争」と「広告費」に強い会社が勝つ時代。
大きな会社は、その資本力を生かして安くて良い商品が作れる。(例:セブンイレブンのスィーツ等)
小さな会社が生き残れるは、商品が良くて高く売れること。(利益率が落ちては、小さな会社はやっていけない。)
しかし、小さな会社会社が得意とする『高い』『良い』という戦略で差別化することが難しい時代になった。
今の世の中は、「足りないものがない。」(商品差がない。)、「情報が多すぎて、覚えられない」(ネットの普及)等。
そうすると、「定番書品を買いたい」(大手のものが安心して買えば、間違いない。)
つまり、『小さな会社が生き残る3ヶ条』は、「必要」と思われる。「記憶」に残る。(覚えてもらう)「愛」を持ってもらう。(その商品を好きになってもらう。)
そして、商品差別が難しい商品は、売り手側と書いての接触頻度を高くする必要がある。
『人』を好きさせるほうが、デザインや商品を好きにさせるようも、売れる確率が高い。
この接触頻度を高めるために、世の中に知ってもらうように宣伝を続けていかなければいけない。
でもお金がない小さい会社では宣伝にかけられるお金は少ないのですが、ブログは有効な認知度を上げるツールだそうです。
以上が今回の講演を抜粋した内容です。
小さな自営業者が行く方向が知ることができて、勉強になりました。
また、次回セミナーに参加したいと思います。

2014年11月15日
やくみやで濃口しょうゆラーメンを食べてみました。
沼津のプラザヴェルデにて行われました第19回静岡健康・長寿フォーラムの昼の時間に、やくみやさんと言うラーメン店に行ってみました。

沼津駅から、徒歩18分、沼津高校の近くにあります。
わざわざ、沼津駅近くのプラザヴェルから歩いて、このお店に行ったのは理由があります。
このお店は、先日放送されましたザ・鉄腕DASHで紹介されたラーメン店だからです。
あの時は、城島さんがこのお店のラーメンを食べていたと思います。
なんでも、スープにあまり手に入らない手火山式かつお節を使ってとかで、興味があったので、行ったしだいです。
お店には11:50くらについたのですが、既にお店の前にお客さんが並んででおりました。
順番で入店していくのですが、次が入店の番になると、店員さんが出てきてメニューを渡して注文を聞いてくれます。
私は、初めての入店なので、何が良いのかわからず、並んでいる人達が口ぐちに注文していた濃口しょうゆラーメンを注文しました。
麺の太さも細麺と太麺があるみたいでしたが、ほとんどの人が細麺を注文していたので、私も細麺にしました。
20分ぐらい外で待ち、入店してイスに座って5分くらいで、注文した濃口しょうゆラーメンが出てきました。

なんとも、手際がよく、好感度が上がります。
さっそく例のスープを食してみると、私にとっては思ったより濃い感じがしなく、比較的あっさりとしたノドごしのあるスープでありました。
スープと細麺の相性も良かったです。
チャシューも多く、口のトロける感じがあり、おいしくいただきました。
小さなお店ですが、店員さんの対応もよく、好感度の高いお店でした。
それにても、全国版のテレビの影響はすごいですねー
私が食べている間や、終わってお店から出てからもお客さんが来ていました。
お店は、本当に小さく目立ったないところにあるのですが、メディアの力はスゴイ なと感じたしだいです。
なと感じたしだいです。

沼津駅から、徒歩18分、沼津高校の近くにあります。
わざわざ、沼津駅近くのプラザヴェルから歩いて、このお店に行ったのは理由があります。
このお店は、先日放送されましたザ・鉄腕DASHで紹介されたラーメン店だからです。
あの時は、城島さんがこのお店のラーメンを食べていたと思います。
なんでも、スープにあまり手に入らない手火山式かつお節を使ってとかで、興味があったので、行ったしだいです。
お店には11:50くらについたのですが、既にお店の前にお客さんが並んででおりました。
順番で入店していくのですが、次が入店の番になると、店員さんが出てきてメニューを渡して注文を聞いてくれます。
私は、初めての入店なので、何が良いのかわからず、並んでいる人達が口ぐちに注文していた濃口しょうゆラーメンを注文しました。
麺の太さも細麺と太麺があるみたいでしたが、ほとんどの人が細麺を注文していたので、私も細麺にしました。
20分ぐらい外で待ち、入店してイスに座って5分くらいで、注文した濃口しょうゆラーメンが出てきました。

なんとも、手際がよく、好感度が上がります。
さっそく例のスープを食してみると、私にとっては思ったより濃い感じがしなく、比較的あっさりとしたノドごしのあるスープでありました。
スープと細麺の相性も良かったです。
チャシューも多く、口のトロける感じがあり、おいしくいただきました。

小さなお店ですが、店員さんの対応もよく、好感度の高いお店でした。

それにても、全国版のテレビの影響はすごいですねー
私が食べている間や、終わってお店から出てからもお客さんが来ていました。
お店は、本当に小さく目立ったないところにあるのですが、メディアの力はスゴイ
 なと感じたしだいです。
なと感じたしだいです。2014年11月11日
第19回静岡健康・長寿学術フォーラムに行ってきました。
先週の土曜日(平成26年11月7日)、沼津市のプラザヴェルデにて第19回静岡・長寿学術フォーラムが開催されたので、行って来ました。

このフォーラムは、健康長寿をテーマに静岡県と静岡県にある公立大学(静岡大学・浜松医科大学・静岡県立大学)が実行委員会となって最新の研究成果と健康長寿について、各地域の取り組みを県民向けに紹介する内容となっております。

午前中は『地域住民のセルフケアを支える人と仕組み』と題して、さまざまな取り組みをされている方が講演されました。
この中で、気づいたことは、昨今は運動の重要性がメディアに紹介されているので、各地域での体操については参加者が増えているようですが、意外と食事について考えていない高齢者が多いことに気づかされました。
それは、タンパク質、つまり肉や魚をあまり食べない方がおり、特に一人暮らしの方にその影響が多いように感じました。
タンパク質は、筋肉や内臓を構成するので、特に高齢になるとこれらが弱ってくるので、タンパク質の摂取は重要だなと感じました。
また、午後のフォーラムでは、東京大学大学院医学系准教授の近藤尚己氏が講演した「ソーシャルキャピル」という言葉に興味をもちました。
「ソーシャルキャピル」とは、人々の間の絆を意味するようで、この「ソーシャルキャピル」が強い地域は、地域住民の健康状態が良いとか、犯罪が少ないなどのメリットがあるそうです。
そして、縦型組織(会社、消防団)より水平型組織(趣味の仲間)の方が、その人にとっては心地よい感じになると教えてくれました。
また、「長寿と心の健康」と題して、静岡県立こころの医療センター院長の村上直人氏から主にうつ病の話をされたのですが、講演の最後に「長寿の人は、何も気にしないタイプの人が長生きするのではなくて、慎重で思慮分別があり、粘り強く、整理整頓が行き届き、準備万端な性格の人の方が、長生きをする。」とおっしゃって、勉強になりました。
今回このフォーラムに参加して、県が長寿社会に関してどんなことを目指しているのか。
また、各地域の取り組みを聞いて、勉強になり、充実した日を過ごすことができました。

このフォーラムは、健康長寿をテーマに静岡県と静岡県にある公立大学(静岡大学・浜松医科大学・静岡県立大学)が実行委員会となって最新の研究成果と健康長寿について、各地域の取り組みを県民向けに紹介する内容となっております。

午前中は『地域住民のセルフケアを支える人と仕組み』と題して、さまざまな取り組みをされている方が講演されました。
この中で、気づいたことは、昨今は運動の重要性がメディアに紹介されているので、各地域での体操については参加者が増えているようですが、意外と食事について考えていない高齢者が多いことに気づかされました。
それは、タンパク質、つまり肉や魚をあまり食べない方がおり、特に一人暮らしの方にその影響が多いように感じました。
タンパク質は、筋肉や内臓を構成するので、特に高齢になるとこれらが弱ってくるので、タンパク質の摂取は重要だなと感じました。
また、午後のフォーラムでは、東京大学大学院医学系准教授の近藤尚己氏が講演した「ソーシャルキャピル」という言葉に興味をもちました。
「ソーシャルキャピル」とは、人々の間の絆を意味するようで、この「ソーシャルキャピル」が強い地域は、地域住民の健康状態が良いとか、犯罪が少ないなどのメリットがあるそうです。
そして、縦型組織(会社、消防団)より水平型組織(趣味の仲間)の方が、その人にとっては心地よい感じになると教えてくれました。
また、「長寿と心の健康」と題して、静岡県立こころの医療センター院長の村上直人氏から主にうつ病の話をされたのですが、講演の最後に「長寿の人は、何も気にしないタイプの人が長生きするのではなくて、慎重で思慮分別があり、粘り強く、整理整頓が行き届き、準備万端な性格の人の方が、長生きをする。」とおっしゃって、勉強になりました。
今回このフォーラムに参加して、県が長寿社会に関してどんなことを目指しているのか。
また、各地域の取り組みを聞いて、勉強になり、充実した日を過ごすことができました。

2014年11月08日
ツボから見た東洋医学(鍼灸治療)5 「得気」と体内の気の関係
前回は、金属性のハリの登場により、操作性と刺激量が自由にコントロールできることを説明しました。
その中で、ハリの刺激量の目標として『得気(とっき)』というハリ刺激によるひびきについて解説しました。
そして、この『得気(とっき)』は、字を読んでのとうりに“気を得る”と記します。
以前のブログ記事で、人間のはく白い息をみて、古代の人は『気』を外にはき出すと思っていたことを説明しました。
人間は、自然界の影響を受け、またその影響で病気が発症します。
皆さんが身近に感じるのは、花粉症ではないでしょうか。
話を元に戻すと、古代の人も自然の影響を受け、その影響で病気になることを知っておりました。
また雲や人間のはく白い息をみて、同じものと考え、それらを“気”と考えたのです。
気の語源は、人間のはく生き、またはご飯を炊くときに出る白い煙、そして自然界に起こる蒸気などです。
そして、これらは動きます。
自然界と人間は同じ『気』で構成されており、気がしっかりめぐることで、自然界では災害が行なくなり、人間においては病気にならないと考えました。
この気の巡りを良くすれば病気にならないという考えを示した治療法が、みなさんご存じの気功法になりますね。
それで、“体の中の気の巡りが良ければ、病気にならない”という考えであれば、ハリ治療でも気を動かすことができれば、健康になると考えるのが自然の流れでは、ないでようか。
そういう訳で、東洋医学には『気一元論』という考えがあります。
これは、自然界、人間は気によって構成されているという考えです。
ハリ治療も東洋医学の一つとたら、ハリ治療によって『得気(とっき)を得て、気を動かすことが重要になってくる』ことが理解できると思います。
2014年11月04日
お気に入りの本『おかげさまで生きる』
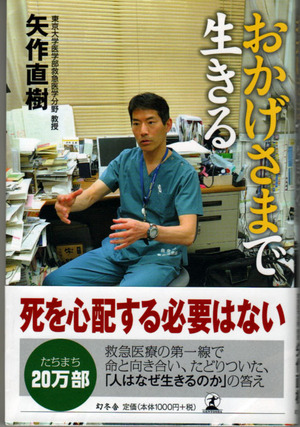
今回、『おかげさまで生きる』という本を紹介します。
著者は、東京大学医学部救急医学分野教授 矢作直樹(やはぎ なおき)氏であります。
矢作先生は、東京大学付属病院の医師でありますが、生と死にいつも直面している救急医学を専門にしているせいか、普通のお医者さんと比較してみると独特な考えを持っています。
例えば、本の冒頭に亡くなった母親と霊媒師の友人を通して会話をしたお話しがでてきます。
それとか、肉体は滅びても、魂は生き続ける等のことを本で述べております。
西洋医学を専攻しているならば、科学的かつ合理的に物事を考えるのが、普通です。
だけれども、生と死が入り混じる救急の世界では、個人の生きる力で生存したり、科学では計りしれない部分もあるのでしょう。
現代の医学では、すべての病気を治すこともできないと本では述べております。
そんな生と死が繰り返される世界にいるせいか、本では『私たちがあの世に持って行けるのは、様々な経験から得た記憶だけ』と言っております。
確かに、自らが築いた財産は、あの世に持っていけませんよねー。
そして、『生きることは、死ぬことあるがままの自分を受け入れ、「すべては学びである」と知る。』とも言っております。
良いことも悪いことも、自分の起きた事として受け入れる覚悟が必要だと説いております。
そして、悪いことは、まず受け入れて、少なからず自分にも原因があることを反省し、反省したら後悔はしない。
大事なことは、今この世界にいる自分は、いくつかの奇跡が起り、この世界に存在している。
だから、私達がやるべきことはたったひとつ、“今を全力で生き、今を全力で楽しむこと”と説いております。
この本を読んでいると、納得することが多く人生の後押しをしてくれる本だと感じます。
また、矢作先生は東大医学部の教授ですが、金沢大学医学部を卒業されていること。
必ずしも東大の教授は、東大出身者でないことも発見できます。
いま巷では、話題の本となっておりますので、ぜひ書店で手にとってみてください。

2014年11月01日
平成26年11月の休診のお知らせ
◇◆◇平成26年11月の休診のおしらせ◇◆◇
◎11月8日(土)は研修の為、休診とさせていただきます。
◎11月20日(木)は研修の為、休診とさせていただきます。
◎11月27日(木)は所要の為、午後の施術を午後4時から始めさせていただきます。
以上間違えないようにお願いします。
◎11月8日(土)は研修の為、休診とさせていただきます。
◎11月20日(木)は研修の為、休診とさせていただきます。
◎11月27日(木)は所要の為、午後の施術を午後4時から始めさせていただきます。
以上間違えないようにお願いします。


